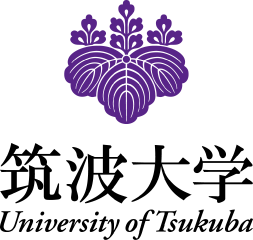- No.33 住吉 美奈子 (SUMIYOSHI Minako)
-
サナテックシード株式会社 管理部
生命共存科学専攻
経歴
| 2009年 | 筑波大学第二学群生物学類卒業 |
| 2014年 | 筑波大学大学院生命環境科学研究科 一貫制博士課程 生命共存科学専攻修了 (博士(理学)取得 |
| 2014年 | 名古屋大学 未来社会創造機構 URA |
| 2015年 | 筑波大学 生命環境エリア支援室 プログラムコーディネーター |
| 2019年 | サナテックシード株式会社 管理部 現職 |
筑波大学を修了するまで
私は筑波大学を始め、たくさんの研究機関が集まるこのつくば市で生まれ育ちました。科学は身近な存在であり好奇心も強かったものの、特に研究者として優れた能力はありませんでした。ただ、とにかくコツコツ続けるのが好きな性格ではあるので、卒業研究から博士号取得するまで植物生理学研究室に所属し、単子葉植物のモデル植物であるイネの細胞壁の構造を明らかにするという研究を行っていました。(一貫制博士過程である生命共存科学専攻(現・環境バイオマス共生学専攻)に進んだので、博士課程の入試がなかったのも大きいかなと思います。)植物細胞壁の研究は基礎研究面がありつつも、人為的に細胞壁改変するというバイオエタノール製造の技術開発につながる応用研究面の性質をもっていたので、科学と社会の在り方を考えるきっかけになりました。
また当時、東日本大震災と原発事故があったこともあり、科学政策としても社会と科学をつなげるサイエンスコミュニケーションの大切さについて耳にすることも多くなりました。なにせ研究学園都市出身なので、何か「科学」というものの役に立ちたいという思いも強かったのだと思います。インターンシップやサークルに参加し子ども向けの実験教室を行なったり、中高生向けの科学雑誌制作にも携わったりと、研究以外の活動も学生時代には夢中になっていました。
大学発ベンチャーで働くようになるまで
私は大学院修了後、名古屋大学や母校の筑波大学URAとして働き始めました。URAは、研究に必要な資金を大学外から調達したり、大学研究者と企業が同じ課題に取り組む産官学連携の推進などを行う、大学の教員でも事務職員でもない「第三の職種」とも呼ばれています。支援するにも、やはり研究の内容が分かっていないと行き届いた支援ができません。なので、修士号や博士号取得者がURAとして採用されることが多いです。(博士号を取っていてよかったです。)
特に筑波大学では、ゲノム編集技術を利用した品種改良のプロジェクトの研究支援をしていました。ゲノム編集技術は新しい技術であることや、生物を「操作」しているということへの抵抗感から、それを利用した作物が流通することに不安の声が上がるとも言われていますが、ゲノム編集技術で引き起こされるような数塩基程度の変異というのは、通常の交配といった品種改良で作られた現在流通する作物でも一般的に起きています。こういったことを社会に理解してもらうにはどうしたらよいのか、ただプロジェクトの支援をするだけではなくて、やはりまた科学技術というものが社会にどのように受け入れてもらえるかを考え行動する機会が多くなりました。このプロジェクトの支援は、植物科学やサイエンスコミュニケーションなど学生時代に身につけたことや、科学ができることを社会に伝えて行きたいというこれまでの思いなどが繋がって働くことができたので、とても幸運に恵まれたと思っています。
私は現在、このプロジェクトで開発されたトマトの商業化を行うために設立したサナテックシード株式会社で働いています。研究支援の先にたどり着いた、自らプレイヤーになる新しい挑戦だと思って日々努めています。

シシリアンルージュハイギャバ
学生の皆さんへ
学生の皆さんに1番に伝えたいことは、自分の人生、いつまでにこう、と決め過ぎなくてもいいのではないか、ということです。理想を持つのは大切ですが、自分の思う通りに進まなくてもそんなに落ち込まなくて大丈夫です。
私は博士課程にも行って、サイエンスコミュニケーションもやりましたが、優秀で研究者として生き残れたわけでもないし、性格的には地味なので、人を惹きつけるサイエンスコミュニケーションで生きていけるとは到底思えませんでした。振り返ってみると、自分の理想に遠く及ばなくても、ただその時その時「やりたいな」と思うことを自分なりに努力してやっていたら、意外なところでつながったと言った方が正しいです。でも今は、この仕事に就くために色んなことを学んできたのかも!と思えるような、充実した社会人生活を今送れています。
研究活動や就職活動が思ったより上手く行かないとか、目標を持って進んでいる人と比べて、自分は何かこれと言ったものを見つけていないなと落ち込んでしまうこともあると思います。今上手くできなくても、頑張っていることを一つずつ進めていけば、将来実を結ぶ日が来るのでどうか焦らずに。

(2021年3月)