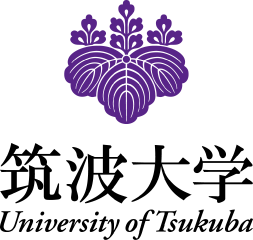- No.13 大野 ゆかり(旧姓 鈴木) (ONO Yukari)
-
東北大学生命科学研究科 日本学術振興会特別研究員RPD
生命環境科学研究科
略歴
| 1997年4月〜2001年3月 | 筑波大学第二学群生物学類 |
|---|---|
| 2001年4月〜2006年3月 | 筑波大学大学院生命環境科学研究科 |
| 2006年4月〜2008年3月 | 九州大学理学部 学術研究員 |
| 2008年4月〜2010年3月 | 東北大学生命科学研究科 博士研究員 |
| 2010年4月〜2014年4月 | 東北大学生命科学研究科 日本学術振興会特別研究員PD |
| 2014年5月〜2016年3月 | 東北大学生命科学研究科 研究支援者 |
| 2016年4月〜現在 |
東北大学生命科学研究科 日本学術振興会特別研究員RPD |
マルハナバチとともに砂利道を行く
学問の世界に、綺麗に舗装された王道があるのであれば、私は間違いなく王道から外れた砂利道を歩いています。砂利道は、いつの間にか雑草が増え、細くなって消えてしまうこともあれば、別の砂利道に合流して大きくなったり、分かれ道があったりと、どうなるのか予想できません。望んでこの道を選んだと言われればそうであり、方向音痴だからこの道から抜け出せないのだと言われればそうでもあります。
筑波大学の大学院で過ごした5年間は、私の研究者としての世界の見方や論理の立て方、研究の興味の対象の基礎を作りました。私は、個体群生態学でマメゾウムシや寄生蜂を使った実験で名を馳せた藤井宏一先生の研究室に所属していました。しかし、藤井研で私の実質の担当教官だった徳永幸彦先生は(私が砂利道を歩くことになる張本人だと思っていますが)、フィールドワークから実験、人工知能までこなす、多才な方でした。そのせいか、私は、実験系の個体群生態学の研究室にいながら、理論生態学者を志し、集団遺伝学の理論や数式を勉強し、ゲーム理論を解析し、動物行動学のモデルを作ったりしていました。このような自由な研究環境は、筑波大ならではだと思っています。
研究テーマを絞らずに、ふらふらと寄り道ばかりしている私に、運命の出会いがありました。毛がフワフワした大型のハチ、マルハナバチです。きっかけは、藤井研で後輩だった川口利奈さん(2018年現在 龍谷大学所属)がマルハナバチを研究していたことです。マルハナバチの巣は地中に作られるため、巣の場所が見つけにくいという話を聞いて、巣の場所を当てるモデルを作ろうと思いつきました。しかし、私は王道ではなく砂利道を歩いていたため、通常の生態学のモデルを使用しませんでした。犯罪地理学で使用されている、犯行現場から犯人の居住地を推定するモデルから着想を得て、マルハナバチを連続犯、採餌をしている場所を犯行現場に見立てて、犯人の居住地域、つまりマルハナバチの巣を当てようと試みたのです。川口さんは、私の無茶振りに応えて、フィールドで詳細なデータを取り、その結果を論文にまとめることができました。こうして川口さんとマルハナバチの共同研究をして以来、マルハナバチはたびたび私の研究対象として登場し、その都度、スランプに苦しむ私を助けてくれました。そうしているうちに、「私はマルハナバチでいいのではないか?」と思えるようになりました。
今では、私の研究の中心にマルハナバチがいます。市民の方々が撮影したマルハナバチの写真を収集し、写真の映像から種同定を行い、写真のGPSデータから撮影場所を特定することで、マルハナバチの分布調査を行なっています(http://meme.biology.tohoku.ac.jp/bumblebee/)。
また、収集したマルハナバチの写真を使用して、人工知能で種同定を行う研究もしています。砂利道を歩いているおかげで、様々な人と出会い、たくさんの方達に助けていただいています。
あなたは、舗装された王道と、雑草の生える砂利道、どちらに立っていると思いますか?王道は先がよく見通せて、確実に歩いていけると思います。一方、砂利道は、時に背の高い草むらや暗い森に視界を阻まれ、不安で足が止まってしまうこともあるかもしれません。それでも、勇気を出して進んでいくうちに、急に目の前が開けて、思いがけず美しい風景が見えることもあります。もし、あなたが砂利道に立っているのであれば、不安かもしれませんが、ぜひ、砂利道の美しさや楽しさを見つけて、歩き続けてください。そのうち、私にとってのマルハナバチのように、素敵な相棒が見つかるかもしれません。そうではなく、王道に立っているのであれば、たまに砂利道をのぞくと、もしかしたら楽しいことが見つかるかもしれませんよ。
おまけ
研究者を目指す学生さんに、私が勇気づけられた言葉を送ります。
「継続できたら天職」 某新聞記者
自分には才能はない、研究者として向いていないのではないか、と考えていた時に、新聞を読んでいて、見つけました。自分にどんなに才能がなくとも、どんなに惨めでも、研究し続けているのだから、才能があるなしに関係なく自分にとっては天職なのだろう、と思うことができました。
「研究者は職業ではなく人生」 三中信宏先生
結婚し、出産し、家族同居を選んで、この先安定的な研究職が望めないと思っていた時に、メーリングリストに流れてきた三中先生のメールのこの言葉を読みました。女性だから我慢しなくてはならない、というのではなく、女性だから自由に、職業としての肩書きが研究者ではなくとも、研究者として生きられる、と思うことができました。