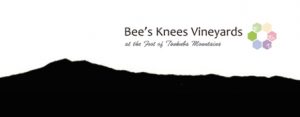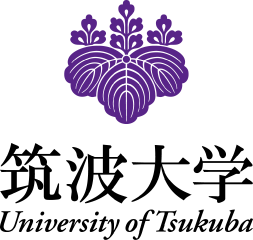- No.12 今村 ことよ(旧姓 磯部) (IMAMURA Kotoyo)
-
株式会社ビーズニーズヴィンヤーズ 代表取締役
生命環境科学研究科
経歴
| 1992年 | 筑波大学第二学群生物学類 入学 |
|---|---|
| 1996年 | 筑波大学生命環境科学研究科 入学 |
| 2001年 | 博士号取得後、三共株式会社入社。研究部門(変形性関節症)に配属 |
| 2007年 | 三共(株)と第一製薬(株)が合併し、所属が第一三共株式会社に変更 |
| 趣味で日本ソムリエ協会ワインエキスパート取得 | |
| 2008年 | 第一三共株式会社 臨床開発部門(骨粗鬆症・関節リウマチ)に異動 |
| 2013年 | 40歳を機に退職、長野県東御市のワイナリーにて栽培・醸造研修へ |
| 2015年 | 新規就農、筑波山麓にてビーズニーズヴィンヤーズ開園 |
| 2018年 | 法人立上げ、個人事業からの移行準備中 |
『生物学は面白い』
卒業生の声ということでお声がけ頂き、寄稿させていただきます。筑波大学に入学後、筑波大学三年の後半に林純一研究室(中田・石川研究室)へと入り、大学院時代にはミトコンドリアとヒトの老化をテーマに研究を行っていました。
おそらく上記の私自身の経歴を見て、なぜこのような現在への道のりを辿ったか不思議に思われる方が多いと思います。私自身も改めて自身の経歴を振り返ってみたいと思います。
高校時代に遺伝学に興味を持ち、ワトソン著の『二重螺旋』を読んだことで、大学で生物学を学ぼうと思ったのだと思います。実家は守谷市(当時はまだ守谷町)でしたので、できれば県内の大学へという両親の希望もあり、筑波大学を第一志望としました。高校時代は利根川を渡り柏市まで自転車通学をしておりましたので、帰宅の際には新大利根橋から筑波山が良く見えました。筑波山というのはとても不思議な山で、その双峰の造形にはその当時からとても惹きつけられました。
一浪し、1992年に筑波大学の生物学類になんとか合格、意気揚々と一の矢宿舎に入寮しました。朝から晩までみっちり生物学の基礎を叩き込まれた一、二年目の授業は本当にどれも興味深かったです。生物学は皆さんもご存知のとおり、実際は非常に多岐の研究分野に渡る学問であると思います。三年次で研究室を決める際、私は将来製薬会社の研究員としてものづくりに関わりたいと考え、ヒトの細胞を用いた研究をしているという安易な理由で林純一研究室の門戸を叩きました。その頃林先生はまだ埼玉がんセンターから筑波大学に移って二年目、実験手法の構築なども手探りで、更に毎週一本英語論文を読んで発表するセミナーが研究室の学生達全員に課せられていました。セミナー前日はほぼ徹夜で論文と対峙していたのを良く覚えています。この頃に、研究者としての目線が相当鍛えられたように思います。
そうして修士に進んだ頃、時代はバブルがはじけ、就職氷河期が始まりつつありました。修士一年時の就職活動の結果は芳しくなく、一方研究は順調だったので学術振興会特別研究員として更に三年大学院に在籍することとしました。そうして大学院後期課程在籍中に三共株式会社の研究職の内定を頂き、2001年から会社員として東京で生活をはじめたのです。
本音を言えば、私自身はつくば市内にあるいずれかの製薬会社に勤めたいと思っていました。ですが、内定が取れなければ致し方ない。これも縁というものだろうと向かった東京というところは、人と建物と物とが雑多に溢れた日本の中心都市でした。満員電車の通勤ストレスなどもありましたが、茨城県を出ること無く28歳となったあの頃の私にとって、都内での暮らしは予想以上に新鮮で、昼間は仕事、夜はあちこちと飲み歩き、ビールや焼酎片手に同僚の方々との付き合いを深め、そして後にワインを飲み始めることとなります。
さて、入社した三共では変形性関節症の研究分野に配属となりました。採用時には癌分野への配属と聞いていたのですが、入社してみたら異なった分野を上司に提示され、企業とはこういう所だから仕方ないという感じで受け入れました。ですが、この軟骨という研究対象は相当の曲者でした。変形性関節症の発症機序は、物理的な摩耗や二次的な炎症で軟骨がすり減っていくというものです。製薬会社なのだから薬剤でこの疾患を治療できなければならない。ヒトとウシの軟骨細胞を相手に三年はかじりついて必死にやろうと思って取り組みましたが、そのうち次第に、この疾患は薬ではなんともならないのではないかと思いはじめました(そして、2018年現在でも変形性関節症の進行を止めたり回復させる薬剤は出ていないので、今思えばこの予感はあながち間違っていなかったと言えます)。
再生医学的アプローチを提案したくとも社内で受け入れられないだろう、という微妙な状況でもありました。他領域への異動希望も出しましたがなかなか通らず、結局7〜8年も骨・関節疾患分野の所属で軟骨の研究に従事する結果となりました。実際、やりたくない研究をやらねばならない状況は研究者としてはかなり辛いものがあります。これが企業勤めだと半ば諦めもあり、その頃、ワインにどっぷりはまっていた私は、昼間の仕事は適度に切り上げて終業後にワインスクールに通うことにして、ソムリエと同等の知識がなければ取得できない「ワインエキスパート」という資格を取得するに至ります。
ワインに関する仕事への転職も良いかもしれないな、などとほんのり思っていたそんな頃、社内でやっと異動が叶いました。臨床開発の部署です。海外から鳴り物入りでライセンスインした抗体医薬でした。今は国内でも上市されている「販売名プラリア(一般名デノスマブ)」という薬で、骨吸収抑制剤と呼ばれるカテゴリに分類される薬剤です。骨粗鬆症領域では海外の臨床試験を参考に国内臨床試験がスタート間近、という段階でした。骨粗鬆症分野の業務を行いながら、この薬を関節リウマチ領域においても、「関節リウマチに伴う骨びらんの進行抑制」という前例のない適応症の承認取得を目指して開発を行う、という大変やりがいのある仕事に関わる事となりました。
関節リウマチチームは当初、チームリーダーと臨床開発経験の全く無い私の2名から立ち上がり、後に開発経験豊富な2名の人員追加となりました。現場の医師の先生方の意見を汲み上げ、社内での逆風もある中、チーム4名一丸となり準備を進めて行きました。社内における事前の根回し、当局(PMDA;(独)医薬品医療機器総合機構)との交渉、臨床試験準備や臨床試験に参加いただく病院への説明回り、臨床試験のスタートアップや試験中の状況管理などなど、それはもう大変な業務量でした。この薬剤を骨粗鬆症以外に、関節リウマチにおける骨破壊抑制としても使えるようにするために、我々がここで踏ん張らなければプロジェクトが打ち切られてしまうのでは、という危機も何度かありました。日本全国を飛び回って行った第二相試験が成功した時、関わって頂いた社内関係者はスタート時の4名から数十人の規模まで増えていたと思います。
そんなプロジェクトで最も私にとって最も面白く、やりがいがあったのは、その作用機作や現行治療におけるこの薬剤の位置づけなど、当局と交渉すべき理論的根拠資料の作成に密に関わらせてもらった事です。しかし今思えば、この仕事があまりにもエキサイティング過ぎました。
異動から数年。第二相試験はわれわれが予想した結果どおりの薬効を示し、見事成功となりました。そうなると次は第三相試験へと進む事になります。私の周りにいた選り抜きの開発マンと呼ばれる同僚の方々は、第三相試験をしっかりと成功させて大きなキャリアを積むことが出来るチャンスだと大変盛り上がっていました。一方、私の心の中はと言えば……、科学的に一番面白かった時期は終わった、こんなにやりがいを感じるような潜在的ポテンシャルを持つ薬剤はおそらく定年まであと一回出会えるかどうかという所ではないのか、と、むしろ寂しさを感じてしまったのです。第三相試験で最も重要なのは、第二相試験の「再現性を取る」こととなります。つまり第二相試験とほぼ同じような臨床試験を、更におおがかりに数年かけて行うことになるのです。もちろん、この第三相試験が成功しなければ薬剤の承認が得られることはありませんので、開発においては大変に重要な部分なのですが、論文を読んで頭を使うよりは、いかにトラブルなく臨床試験を遂行させるかという管理業務が中心となり、サイエンス的側面はあまり必要なくなって行きます。
そんな時、また頭をよぎったのは再びワインの事でした。日本国内でワイナリーを立ち上げた方の書いた本を読んで感化され(今思うと安易だったのではとも思うのですが)、もしワイン造りに関われるのであれば、会社を辞めてまでもその世界に飛び込む価値が大いにあるような、魅力的な仕事と思えました。会社で働き続けたまま、国内の中規模ワイナリーをいくつか訪問する中で、ブドウ栽培にこだわり、自社栽培のブドウを中心としてワインを醸造している長野県のワイナリーに通い、一年を通して栽培と醸造を見せていただく機会を得ました。目の回るような忙しさの中、月に一、二度長野に新幹線で通い、畑で、醸造蔵で目にしたものは、実際のところ予想以上に密接に生物学が関与するものづくりの現場だったのです。
栽培には植物生理学に加えて、害虫や病気や農薬の知識に、土壌学や雑草の年間遷移、醸造となれば酵母によるアルコール発酵、乳酸菌によるマロラクティック発酵などをすみやかに終わらせるための微生物学的知識が必要で、果汁の酸や糖度などの分析なども行います。長野に通う毎に、この仕事をなりわいとしたいと強く思うようになっていきました。
そして。ワイン造りを目標とすれば、つくばに戻って来ることが出来るのではないか。そう考えたのも動機のひとつです。つくば市のどこでならワイン用ブドウの栽培が可能だろうかと色々調べてみると、気候としてはブドウ産地としては夜温が下がらず、少々冷涼さに欠けるように思われたのですが、筑波山麓には花崗岩が崩壊して積もった独特の土壌がありました。花崗岩土壌は海外のワイン銘醸地、伊のサルディーニャ島や、仏のアルザスやローヌ地方などでも見られる、水はけのよい、ミネラル分の豊富な土壌なのです。筑波山麓にワイン用のブドウ品種を植えたらどんな味わいとなるのだろうか。気候的にはシャルドネやカベルネ・ソーヴィニヨンと言った品種、そしてローヌで作られているシラーを植えてみたい。そしてそれらのブドウから出来るワインを味わうとしたら、おそらく自分で植樹してワインを作るのでなければ、他の誰もそのようなチャレンジをする事は無いだろうと思いました。
そこまで考えて、私は製薬での仕事とワイン造りの仕事のどちらを取るかを天秤にかけ、ワイン造りの仕事に挑戦してみることにしました。「やりたいことがあるのに、やらないという事の意味が分からない」と、夫が背中を押してくれたという事もあります。夫は今迄ただの一度も、私のこの取組に対して反対したことがありません。何故か長野での栽培醸造修行にもついてきて長野から東京の会社に通勤し、つくばに越してきた今も同じ会社で働き続けてくれています。これは無収入期間が長くなりがちな、果樹での新規就農を選択した私にとって、大変心強いことでした。
一年半の長野での研修生活の後ですが、2015年の1月より、とうとう念願のつくばに移住してその年からブドウ苗を植樹を開始しました。ボランティアの方々と共に三年間で約4000本の苗の植え付けを行い、畑の広さも1.5ヘクタールまで広がりました。将来的に、これらのブドウ樹から1万本弱のワインが出来てくる予定です。2017年秋には植樹三年目のブドウ樹から、1トン弱のブドウをやっと収穫することができました。そして今春瓶詰めされたばかりの赤ワインと白ワインが、今私の目の前にあります。
会社を辞めると言ったのは5年前のちょうど今頃です。この5年で、私が関わる筈だった第三相試験は無事に成功を収め、去年、関節リウマチ領域においても無事当局より承認されました。この薬の関節リウマチにおける適応は、全世界で日本のみが取得している状況です。海外のKey Opinion Leaderの医師達からもその成果を絶賛されたと聞いています。そのお祝い会に私も呼んで頂き、2016年に取れたわずか120kgブドウから作ったスパークリングワインを手にかけつけました。会社を辞め途中でプロジェクトを離脱した私にとっても、この薬剤の承認取得はとても嬉しかったですし、そしてその場に集まった皆さんも、私が4年半の成果としてなんとかかんとかワインを作りあげたことを手放しに喜んでくれました。
私のこの方向転換が果たして正解であったのかどうなのか、それは私の人生が終わる時に自分で分かる事だろうと思っていますが、興味を持ったことはとことん突き詰めて対峙して来た事が幾重にも積み重なり、今の自分を作っているのだと、そう思います。
つくばに戻って来て、学生時代に知り合えなかった筑波大卒業生と知り合う機会にも多く恵まれ、充実した日々を送っています。成果が出せなかった研究員時代と、薬の上市に関わることができた開発時代は今となってはどちらも良い経験です。その両方があって、こうして私はつくばにいます。
畑で作業をしながら、ブドウの植物生理や土壌微生物の事を考えるのが、何よりも楽しい時間です。『フィールドサイエンス』として、栽培から醸造の一連に関わる様々な事象がどれも面白い研究対象であり、仮説をたて推論を行いながら日々のブドウ栽培と収穫後の醸造作業に向き合っています。論文などはそうそう書けないとは思いますが、私にとって何よりも嬉しいのが、毎年その成果がワインとなって瓶詰めされることです。ワインというのはその年の気候がストレートに味わいに出てきます。毎年の気候の違いや、ブドウ樹が年々成長することで、より力強いワインになっていく様を飲んでくださる皆さんと共有できたら、そしてワインの楽しみ方をもっと皆さんにもお伝えできれば、これ以上嬉しいことはありません。そして、いずれ醸造所も立ち上げようと市役所や県の機関など調整に回ったりもしているのですが、そんな時には会社員時代の経験に助けられているなとしみじみと思うのです。
私の進路は色々と変わりましたが、ひとつだけ変わらないのは、大学入学以降、ずっと様々な「生物学」が私の頭の中の大半を占めていて、それが興味深い、素晴らしい学問であり、私の生きる原動力であるということです。
本当に生物学は面白く、知識欲は逗まるところを知りません。大学院に在学する皆さんにも、このわくわくする気持ちを常に持って充実した学生生活を、そして将来の社会人生活を日々過ごして頂きたいなとそのように思います。
もし機会があれば、皆さんにもいずれ出来るワイナリーにもぜひ足を運んでいただければと思います。筑波山麓のブドウ畑で、皆さんのおいでをお待ちしております。
リンク