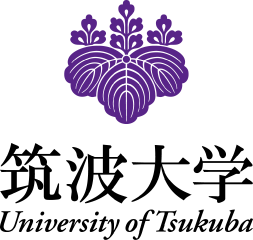- No.07 山口 晴代 (YAMAGUCHI Haruyo)
-
国立研究開発法人 国立環境研究所
生物・生態系環境研究センター 研究員
構造生物科学専攻 【現 生物科学専攻】
経歴
| 2006年 | 筑波大学第二学群生物学類 卒業 |
|---|---|
| 2008年 | 筑波大学大学院 博士前期課程 生命環境科学研究科生物科学専攻 修了 |
| 2011年 | 筑波大学大学院 博士後期課程 生命環境科学研究科構造生物科学専攻 修了、博士(理学)取得 |
| 2011〜2014年 | 日本学術振興会特別研究員 PD |
| 2014年〜 | 現職 |
私は、筑波大学で博士号を取得した後、3年間の国立環境研究所での日本学術振興会特別研究員PD(*1)を経て、現在、同研究所の研究員として勤務しています。現在の仕事内容は、研究業務と研究以外の業務に分けられます。研究では、環境問題の原因となる藻類、とくにアオコを形成するシアノバクテリアの遺伝子解析を行っており、研究以外の業務では研究所にある藻類カルチャーコレクションの運営を行っています。研究所には世界で活躍されているさまざまな環境分野の研究者がおり、毎日刺激を受けながら研究をしています。またフレックスタイム制度や病後児も受け入れ可能な一時保育室の整備など働きやすい環境作りも行われており、安心して仕事に取り組むことができます。
私は高校生のときから現在まで一貫して、藻類を対象に研究を行ってきました。生物学類には高校生のときに行った藻類の研究成果をもとにAC入試(*2)で入学し、大学1年生から博士号を取得するまでの9年間、藻類の系統分類学で著名な井上勲先生(現筑波大学名誉教授)にご指導戴きました。その当時は、大学1年生を公式に研究室に受け入れるシステムはありませんでしたが、井上先生のご厚意で大学1年生から研究室のセミナーやサンプリングに参加させていただいたり、研究室の設備を利用させていただきました。これまで井上先生にはさまざまな事を教えていただきましたが、その中でも特に鍛えていただいたのが、作文とプレゼンテーションの作り方です。「藻類のことなんて誰も知らない。知らない人にもわかってもらえるように」と私が書く申請書や論文、プレゼンテーションを毎回何時間もかけて添削してくださいました。井上先生から返ってきた真っ赤な原稿を見る度に、私の書く文章がいかに他者への思いやりのないものであったかと反省したものです。また、藻類は多様であるため、藻類を理解するには、藻類に近縁な原生動物や菌類の理解も必要で、また、学問領域としても分類学、分子生物学、生態学、古生物学などを総合的に理解しなければならないことを常日頃学生に説いて下さいました。しかし、自分一人でこれらの勉強をするのは大変です。そこで、楽しく勉強できる方法はないかと考えて出した結論が分野横断セミナーの開催です。2007年からいわゆるプロティスト(藻類と原生動物)を扱う近くの研究室の先生たちに声をかけて「つくば藻類・プロティスト研究フォーラム」と称するセミナーを始めました。このセミナーを通して、藻類をまるごと理解することの重要性、ひいては物事を複数の視点からみることの大切さを学ぶことができました。
社会に出てからも、大学や大学院のときに行っていた研究内容をそのまま続けられる人はほんの一握りだと思います。だからといって、大学院までにやってきた研究は決して無駄ではなく、大学院で過ごす中で身につけた作文能力、プレゼンテーション能力、物事を複数の視点からみる能力は社会に出てもとても役立ちます。博士号を取得してからも藻類という研究対象を変えていない私でさえ、藻類の専門知識と同じくらい、これらの能力が大事であると痛感しています。大学院ほど少人数で懇切丁寧に指導を受けられる機会はほとんどないと思いますので、これから筑波大学生命環境科学研究科で学ばれる学生さんたちは、この又とない機会を利用して、指導教員の先生のお話をよく聞き(私自身が一番聞いていなかったかも知れませんが)、純粋な心で研究に没頭してみてください。
また、ライフ・ワーク・バランスも大切です。この先、家事や子育て、介護などで思うように仕事に時間がとれないことも出てくるかも知れません。そんなときには、自分の中で優先すべきことを決め、すべてを完璧にすることを諦めることも重要ではないかと思います。
*1) 日本学術振興会特別研究員制度
*2) AC(アドミッション・センター)入試・・・筑波大学で採用している自己推薦型入試制度でそれまでの活動実績を評価 するのではなく、「問題解決能力」が評価される入試選抜方法